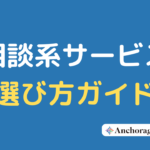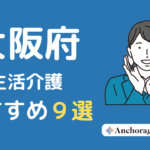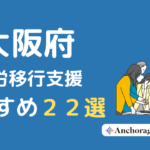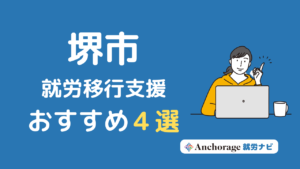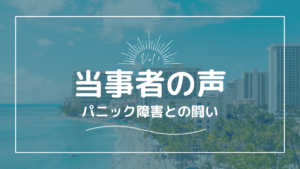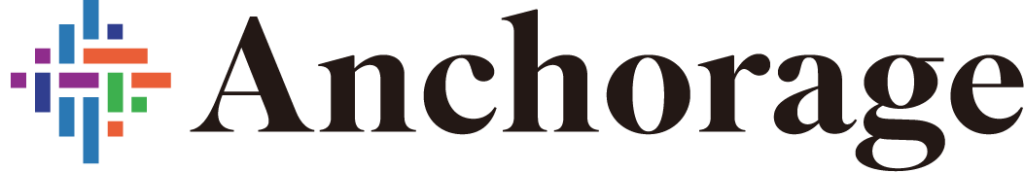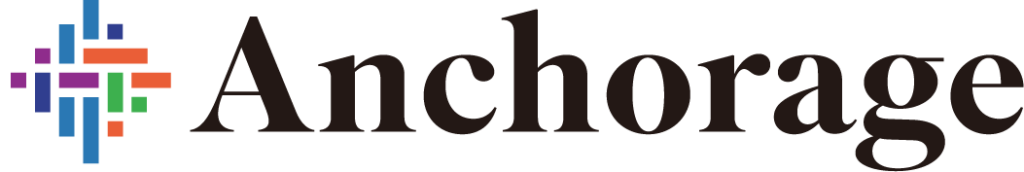目次
「寝ても寝ても眠い…」それ、うつ病のサインかも?
「しっかり寝ているはずなのに、日中もずっと眠い」「昼寝をしても疲れが取れず、余計にだるくなる」——こんな症状が続いていませんか?単なる睡眠不足ではなく、うつ病が原因で強い眠気を感じている可能性があります。
うつ病といえば「不眠」のイメージが強いですが、実際には約40%のうつ病患者が「過眠(寝すぎ)」の症状を抱えていると言われています。特に、日中に長時間寝てしまう「デプレッションナップ(Depression Nap)」が問題視されており、生活の質を大きく低下させる原因になります。
本記事では、うつ病による過眠の原因やその影響、適切な対処法を詳しく解説します。「なぜこんなに眠いのか?」と悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
うつ病と睡眠障害の関係とは?
うつ病で「異常な眠気」が起こるメカニズム
うつ病の症状として広く知られているのは「不眠」ですが、実はその逆の「過眠」もよく見られます。では、なぜうつ病になると日中の眠気が強くなるのでしょうか?

1. 脳のエネルギー消費が低下する
うつ病になると、脳の働きが低下し、エネルギーを節約するように適応します。そのため、日常的な活動ですぐに疲れを感じ、「とにかく眠りたい」という状態になりやすいのです。
2. セロトニンとメラトニンのバランスが崩れる
脳内ホルモンであるセロトニン(幸せホルモン)は、気分の安定だけでなく、睡眠リズムを整える役割も担っています。うつ病になるとセロトニンが不足し、その影響で睡眠ホルモンのメラトニンの分泌も乱れるため、昼間でも眠気が取れなくなります。
3. 睡眠の質が低下する
うつ病の人の睡眠は、深い眠り(ノンレム睡眠)が少なく、浅い眠りが増える傾向があります。その結果、「寝ても疲れが取れない」「朝スッキリ目覚められない」といった状態になり、日中の過眠につながります。
4. 身体的な疲労ではなく、精神的な疲れが影響する
通常の眠気は、身体を動かした後に起こるものですが、うつ病による眠気は「精神的な疲れ」が主な原因です。「特に何もしていないのに疲れている」「動こうとすると強い眠気が襲ってくる」という場合、うつ病の影響が考えられます。
「うつ病の過眠」と「普通の昼寝」の違い
「昼寝をするのは悪いことではないのでは?」と思うかもしれません。確かに、適度な昼寝は健康に良いとされています。しかし、うつ病による過眠と、単なる疲れによる昼寝には明確な違いがあります。
うつ病による過眠の特徴
✔ 昼寝をしてもスッキリしない、むしろだるくなる
✔ 1時間以上寝てしまい、目覚めても眠気が取れない
✔ 夜の睡眠が浅く、途中で何度も目が覚める
✔ 気分の落ち込みや無気力感が続く
疲れによる昼寝の特徴
✔ 20〜30分の短時間でスッキリする
✔ 肉体的な疲れが原因で眠くなる
✔ 週末にしっかり休めば改善する
✔ 昼寝をしなくても日常生活に支障がない
このように、昼寝をしても疲れが取れない、気分が落ち込むような場合は、うつ病の可能性が高いため注意が必要です。
うつ病による眠気を軽減する方法
1. 昼寝の時間を調整する
昼寝自体は悪いことではありませんが、うつ病の人は長時間眠ることで症状が悪化する場合があります。 適切な昼寝のポイントは以下のとおりです。
✔ 昼寝の適切なポイント
- 昼寝は20〜30分以内に抑える(長時間の昼寝は夜の睡眠を妨げる)
- 昼寝は午後3時までに済ませる(それ以降は夜の睡眠に悪影響)
- コーヒーナップを活用する(昼寝前にカフェインを摂るとスッキリ目覚められる)
2. 朝に日光を浴びる
朝日を浴びることで、セロトニンの分泌が促され、体内時計が整います。 毎朝10〜15分でもいいので、ベランダや外で日光を浴びる習慣をつけましょう。
3. 軽い運動を取り入れる
うつ病の人は体を動かすのが億劫になりがちですが、軽い運動をすることで眠気を軽減できます。特に、朝のウォーキングやストレッチは効果的です。
4. 専門家に相談する
「昼間の眠気がひどすぎて日常生活に支障が出る」場合は、心療内科や精神科の専門医に相談するのがベストです。適切な治療を受けることで、症状が改善することもあります。
まとめ:眠気に悩むなら、まずは生活習慣を見直そう!
うつ病による眠気は、脳の機能低下やホルモンバランスの乱れが原因で起こります。そのため、生活習慣を整えることで改善できるケースも多いです。
✅ 昼寝は20〜30分以内に抑える
✅ 朝に日光を浴び、体内時計を整える
✅ 軽い運動を取り入れ、日中の眠気を軽減する
✅ 規則正しい生活を意識する
✅ 必要なら専門家に相談する
「最近、日中の眠気がひどくて困っている」という方は、今日から少しずつ生活習慣を見直してみましょう。 眠気が軽減されるだけでなく、心の状態も安定しやすくなります。